「パーフェクトな意思決定」とは
「パーフェクトな意思決定」は、シリーズ150万部を突破した「リーダーの仮面」「数値化の鬼」「とにかく仕組み化」の著者であり、株式会社識学の代表である安藤広大氏の最新本です。
本書では、
「自分の責任に応じて、意思決定ができること」
「決めたことに対して100%実行すること」
「つねにいい結果を出そうとするのはもちろん、もしいい結果が出ないときは、最初の意思決定を疑い、次なる意思決定ができること」
が目的に記されています。
詳しい内容は本書を参照していただくとして、ここでは、序章に記されている「パーフェクトな意思決定」をする上での心構えをまとめてみました。
なぜ「決めること」は恐いのか?

ほとんどの物事は、賛否両論で構成されているからです。
つまり、あなたが何かしらの決断をすると、賛成する人がいる反面、必ず否定的な意見を言う人がいることを理解しておきましょう。
決断した人を尊重する

では、なぜ賛否両論の「否」が存在するのでしょうか。
それは、人は文句を言う生き物であり、自分のことはさておいて、他人のことにはあーだこーだ言いたくなるからです。
したがって、何かを決断する際には、そのような否定的な人を無視するしかありません。
ただし、あらかじめその人から情報共有があった時には、その情報に耳を傾けることで、一方的に文句を言われることがなくなる可能性があります。
一方、決めてもらう側の人は、決断した人のことを尊重することが大切ですね。
「チャレンジした人が偉い」のであり、その結果たとえ失敗しても「失敗した人が偉い」のです。
このように、決める時には何かしらの苦しみが生じるものです。
その苦しみを理解できる人になりましょう。
決断しないことの弊害

決めることが恐かったり、面倒だったりすることで決断を先延ばしすると、決めないことによる機会損失が発生します。
特に、企業の場合はそれが顕著で、一見すると業績が停滞するだけに感じますが、未来への損失は確実に生まれていることを理解しておかなければなりません。
特に、日本人の場合、社内や社外からの提案に対して「検討します」を多様しがちです。
ところが、「検討します」は遠回しの断り文句であり、実際は何もしないのが大方ではないでしょうか。
無闇に「検討します」を口走るのは、全裸より恥ずかしいことと心得ましょう。
人は現状維持を好む
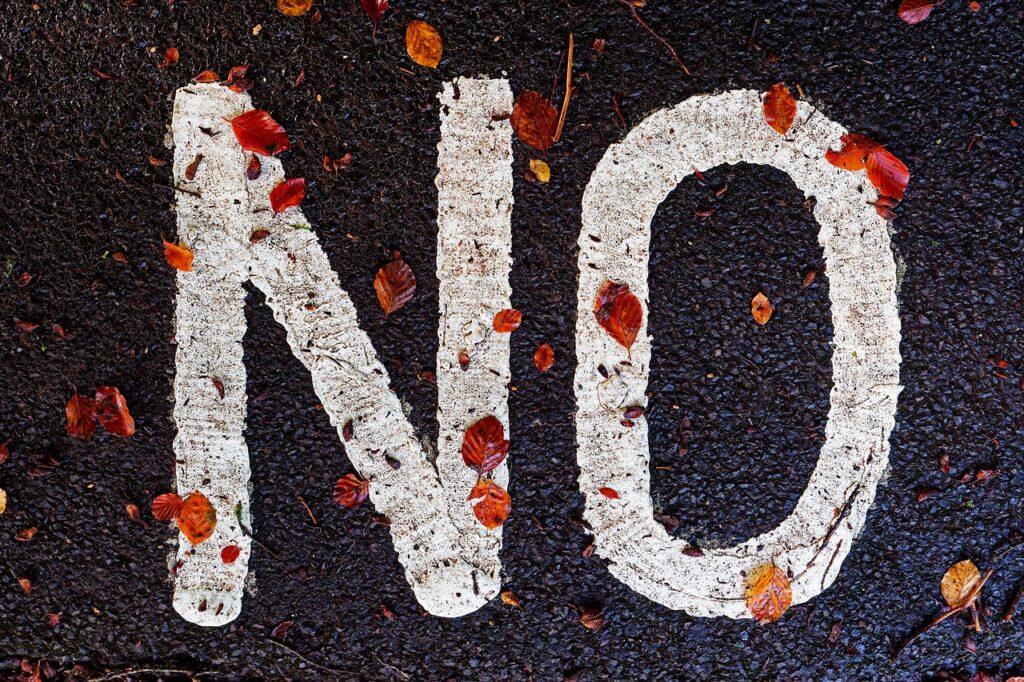
新たなことを始めようとすると、必ずと言っていいほど否定的意見が飛び出します。
なぜなら、人は現状を好む生き物だからです。
一般的に、多くの人は変化を嫌う傾向があり、「前の方が良かった」と思うのもその一例です。
しかし、動かなければ(決断しなければ)成功はあり得ませんし、たとえ動いて失敗したとしても、その失敗からは改善策が生まれます。
最も忌み嫌わなければならないのは、何もせずに現状を維持することです。
主体的にそうするのであれば問題ありませんが、ただ何となく先延ばしする状況だけは何としても避けなければなりません。
決めない状態は気持ちいい

決める前にはいくつもの選択肢があり、その多くの選択肢があることに人々は満足しがちです。
しかし、いつかは決めなければならない瞬間は必ず訪れます。
先延ばしすることから生じる気持ちよさはあくまでの錯覚であり、一刻もその状況から逃れることが、結果的には正常な精神状態を保てることにつながります。
・決断した人を尊重する。例えその決断が間違ったとしても、決められる側には攻める権利はありません。
・「検討します」を口にするのは、全裸より恥ずかしいことと心得ましょう。
・決断する癖を身につけることで、先延ばしする習慣からさよならしましょう。
豊かな人生を構築する

誰かに決めてもらうよりも、自らが決断した人生を堂々と歩みませんか。
時には、その決断より失敗を招くこともあるかもしれません。
それでも、自ら決断した人は、失敗さえも自分の成長に変えることができます。
一方、誰かに決められた人生はあまりにも味気なく、最終的には虚しい人生という末路が待ち構えます。
ぜひ、あなたも「パーフェクトな意思決定」を実践して豊かな人生を構築しましょう。

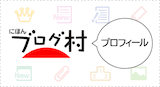






コメント